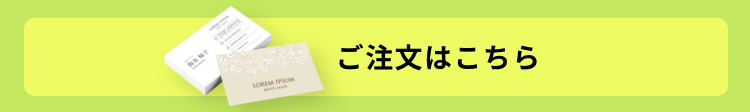コラム
匂いで記憶がよみがえる「プルースト効果」とは?香りと脳の関係をわかりやすく解説

あなたもコーヒーの匂いで祖母の家での温かい記憶が蘇ったり、塩素の匂いでプールでの楽しかった思い出が瞬間的に心によみがえったりした経験はないでしょうか。
このように特定の匂いによって過去の記憶や感情が鮮明に蘇る現象を「プルースト効果」と呼びます。今回は、なぜ匂いだけが記憶と強く結びつくのか、そのメカニズムから日常生活での活用方法まで詳しく解説します。
Index
匂いで記憶が蘇る現象の「プルースト効果」とは?
プルースト効果とは、特定の匂いを嗅いだ瞬間に、その匂いと結びついた過去の記憶や感情が鮮明によみがえる現象のことです。フランスの文豪マルセル・プルーストの小説『失われた時を求めて』で、主人公が紅茶に浸したマドレーヌの香りを嗅いだときに、子ども時代のお母さんとの記憶を思い起こした描写から名付けられました。
匂いから得た情報は、ときとして視覚から得る情報以上に深くその人の心に刻まれます。あまり身近に感じないかもしれませんが、だれもが体験できる現象です。次では、具体的に例も見てみましょう。
【関連記事】プルースト効果ってどんな現象なの?活用できる方法と一緒に解説白
日常でよくあるプルースト効果の具体例
プルースト効果は、日常生活のさまざまなシーンで体験している現象といわれても腑に落ちない方も少なくないはずです。しかし、実際には以下のような体験をした方がほとんどではないでしょうか。
- 香水の匂いで昔の恋人を思い出す
- 食べ物の匂いで幼少期の家族との記憶が蘇る
- 花や植物の匂いで特定の季節や場所を感じる
- 場所特有の匂いで訪れた場所を思い出す
- 人の匂いで特定の人物を想起して印象を感じ取る
- 特定の匂いで乗り物や機械を思いつく
どうでしょうか。名前こそ難しく聞こえますが、実際には私たちの生活に深く根ざした身近な現象だったはずです。プルースト現象というのは、記憶の扉を開く鍵のような「匂いが持つ働き」を示しているのです。
匂いが記憶に残りやすい理由

匂いが記憶に残りやすいのは、嗅覚が「感情と結びつけて即行動できる状態を作る」仕組みを持っているからです。通常、視覚は情報量が多く、聴覚は時系列で記憶されやすいという特徴があります。
一方で、匂いは感情と記憶を同時に呼び起こす特別な性質があります。匂いというのは「腐っている」、「毒がある」、「敵や獲物が近い」などの生存に直結する情報を伝える役割もあるからです。
一種の生存本能に関わる機能だと考えてください。「考えて判断」していたら命に関わる場面では、匂いによる瞬間的な判断を求められるはずです。生きるための役割が長い年月を経ても現代人に残っており、今でもなお匂いと記憶の強い結びつく能力を持っているのです。
匂いと脳の記憶が結びつく仕組みをわかりやすく解説
匂いが記憶と結びつく仕組みを理解するには、匂いが脳に届くまでの5つのステップを知らなくてはなりません。可能な限り簡単に説明しているので、この機会にぜひ覚えてみてください。
1. 匂いを吸い込む
まず、匂いと脳の記憶が結びつく仕組みは、鼻の中にある「嗅覚受容体(きゅうかくじゅようたい)」に匂い分子がくっついてからスタートします。この嗅覚受容体は、鼻の中の「匂いキャッチャー」のような存在だと考えてください。
この受容体に匂いの分子が付着すると、「この匂いは○○だ!」という信号を発信します。人間は多種類の受容体を持っており、その組み合わせによって信号をわけて匂いの違いに気づきます。
2. 匂いの信号を脳へ送る
次に、受容体から送られた匂いの信号は「嗅球(きゅうきゅう)」という脳の中継所を経由して、すぐに以下の場所に直行します。
- 感情をつかさどる場所
- 記憶をまとめる場所
鼻から来た匂い信号の最初の中継所であるこの嗅球が、視覚・聴覚と大きく違う点です。通常、視覚や聴覚の情報は理解・認識を担う大脳皮質を通ります。
しかし匂いは大脳皮質をショートカットし、感情や記憶を直接刺激するのです。
3. 感情と結びつける
こうして届いた匂いは扁桃体を刺激し、「懐かしい!」、「楽しい!」、「嫌だ!」といった感情を一気に引き起こします。この扁桃体は「感情のスイッチ」のような働きをし、怖い・嬉しいなどの感情が動く場所です。
匂いが素早く扁桃体に届く結果、理屈抜きで感情を動かす刺激となって記憶に残ります。感情的で強烈な匂いというインパクトは「考えるより先に感情を呼び起こす」仕組みとして、長い人生のなかで徐々に記録として蓄積します。
4. 記憶の引き出しが開く
記録として蓄積した『匂いの記憶』は、同じ匂いを感じ取ると『当時の感情』を呼び起こします。この感情が動くと同時に出来事の記憶づくり・取り出しを担う海馬を刺激し、過去の出来事の記憶(自伝的記憶)を呼び起こします。
なお、呼び出す記憶は匂いに紐づいていますが、「子ども時代の古い記憶」を呼びやすいことが研究で判明しています。
5. 鮮明に追体験する
最後に、呼び出された記憶は、ほかの手がかり(言葉や写真)よりも、より鮮明で感情を伴う情報として私たちが理解・認識します。まるでその場に戻ったかのような臨場感でよみがえる追体験、これが「プルースト現象」と呼ばれる仕組みです。
- 匂いを吸い込む
- 匂いの信号を脳へ送る
- 感情と結びつける
- 記憶の引き出しが開く
- 鮮明に追体験する
ここまでお伝えした上記の一連の流れを素早く処理して、匂いと記憶の特別な結びつきを生み出しているわけです。
匂いと記憶を呼び起こすプルースト効果の注意点

匂いと記憶を呼び起こすプルースト効果は、身近で体験できる現象ではありますが万能ではありません。以下では、知っておきたい注意点も紹介します。
効果には個人差がある
プルースト効果が引き起こす匂いに対する感受性や好み、過去の経験は人それぞれ異なります。例えば、ラベンダーにリラックス効果があるとしても、その匂いが嫌いな人にとっては意味がありません。
匂いに好みが存在する以上、一定の傾向はあっても完璧に『だれでも良いイメージを想起する』という画一な答えはないわけです。同じ匂いを嗅いだ体験であっても、人によって呼び起こされる記憶や感情はまったく違い、受ける印象も異なります。
TPOによっては合わない
匂いは自らだけに限らず他人にも影響を与えるため、TPOに合わせて使用する場所や強さに注意してください。学校や職場などの一部の場所では気軽に匂いを取り入れられませんし、アレルギーを持つ人にも配慮が必要です。
また、臭いを取り入れられるとしても、適度な強さで周囲に迷惑をかけない範囲での使用が好ましいです。公共の場では特に、ほかの人の記憶や感情にも影響を与える可能性を考慮してください。
ネガティブな記憶も呼び起こす
気がついた方もいるかもしれませんが、すべての匂いが良い記憶と結びついているわけではありません。トラウマや嫌な体験と結びついた匂いは、かえってストレスや不安を引き起こします。
匂いを活用する前に、自分にとってどのような記憶と結びついているかは深く考えるはずです。しかし、他人は実際に試さないと分からない領域であるため、ネガティブな印象がないかはよく調べて取り入れてください。
匂いと記憶を結びつけるプルースト効果の活用例

注意点こそあるものの、匂いと記憶を結びつけるプルースト効果を正しく理解して使えば、さまざまな場面で私たちの生活を豊かにしてくれます。ここでは、具体的な活用例を紹介します。
恋愛
好きな人の匂いは、だれしも強烈に記憶に残っているのではないでしょうか。恋愛において匂い、つまり相手の体臭や香水は感情と強く結びつき、別れた後でも同じ匂いを嗅ぐと当時の感情が蘇るものです。
これは扁桃体が感情処理を担って、恋愛感情という強い情動を匂いと一緒に記憶するからです。個人差はありますが、逆に考えれば恋愛関係では意図的に特別な匂いを共有し、より深い絆を作ることも可能なわけです。
勉強
勉強中に特定の匂いを使用し、テスト本番でも同じ匂いを身につければ、記憶の定着と想起を促進するといった使い方も可能です。実際の研究で、ローズマリーの匂いが記憶力向上に効果を示したという研究もあるほどです。
ここで重要なのは、自分にとって良い記憶と結びついた匂いを使うことです。また、科目ごとに異なる匂いを使いわけ、脳内で情報を整理しやすくする方法も一考の余地があります。
医療・介護
プルースト効果は、思い出や感情を呼び起こす効果がある性質から、認知症の症状を改善する場面でも使われはじめました。一般的に認知機能が低下した高齢者でも、嗅覚に対する反応は生存本能に近く、記憶に保たれやすいからだと考えられます。
例えば、懐かしい匂いを使って記憶を刺激する「回想法」は、医療現場でよく使われる方法です。患者の生い立ちや好みに合わせた匂い(故郷の花、好きだった食べ物の匂いなど)を使用し、過去の記憶を呼び起こして認知機能の維持や改善を図る取り組みも行われています。
ビジネス
現代のマーケティングやブランディングにおいて、プルースト効果を活用した「香りマーケティング」も注目したい方法です。ホテル、ショールーム、店舗などで独自の匂いを使用し、顧客が「この匂いを嗅ぐとあの会社を思い出す」という状況を意図的に作り出します。
企業のイメージを匂いで記憶に残す効果が期待でき、競合他社との差別化と顧客ロイヤルティの向上を図れます。香りマーケティングについては、以下のページでも詳しく触れているためぜひ参考にしてください。
【関連記事】癒しの香りは何がある?メリットからおすすめ・ビジネスへの取り入れ方まで解説
匂いをビジネスに取り入れるなら『香り印刷』がおすすめ
匂いと記憶を強く結びつけるプルースト効果をビジネスに活用したい方は、弊社の香り印刷サービスもぜひご覧ください。香り印刷では特殊なインキで香りを封じ込め、名刺やチラシ、ハガキなどに匂いを付けることができます。
印刷時に付与した香りは擦るとより匂いが強くなる仕組みで、カプセルが割れない限り長期間持続します。清楚なラベンダーブーケから鮮烈レモン、芳醇ローズまで14種類の香りをご用意しており、ビジネスシーンに合わせて選択可能です。
例えば、名刺交換時に香りがする名刺なら相手に強い印象を残すことができ、プルースト効果によって思い出してもらえるでしょう。情報が氾濫する現代だからこそ、匂いという五感に訴える手法で他社との差別化を図るきっかけにしてください。
匂いと記憶に関係するよくある質問(FAQ)

最後に、匂いと記憶、そしてプルースト効果について、よく寄せられる質問へ回答します。
匂いが記憶に残るのはなぜ?
嗅覚の情報がほかの五感と異なり、感情や記憶を司る大脳辺縁系に直接伝わるためです。視覚や聴覚は理性的な処理を受けますが、嗅覚は本能的な脳領域にすぐにアクセスし、記憶や感情と強く結びつく特別なルートを持っています。
扁桃体および海馬体は、それぞれ情動および記憶システムの一部としてヒトの高次精神機能に重要な役割を果たしています。平たくいえば、匂いだけは「心に直通する特別ルート」を持っており、理屈より先に感情や思い出を呼び覚ます力を持っているのです。
プルースト現象とプルースト効果の違いは何ですか?
プルースト現象とプルースト効果は基本的に同じ現象を指す用語で、明確な違いはありません。学術的な文献では「プルースト効果」がより一般的ですが、どちらを使っても意味は同じと考えてください。
「プルースト現象」は現象そのものを、「プルースト効果」はその効果や影響を強調した表現として使うケースも見られます。
匂いが記憶に残りやすい順番は?
個人差がありますが、一般的に感情と強く結びついた匂いほど記憶に残りやすい傾向があります。
主に、恋愛関係の匂い、幼少期の家庭の匂い、特別な体験と結びついた季節の匂いなどが特に印象深い記憶として残りやすいです。ただし、良い・悪いに関係なく記憶に残る点には留意してください。
匂いの記憶を消す方法はありますか?
完全に消すのは困難ですが、その匂いと新しい良い体験を結びつけて印象を変えることは可能です。時間の経過、意図的な回避、専門家によるカウンセリングなどの方法があり、感情的な強度は自然に薄れていく場合もあります。
もし、ネガティブな匂いの記憶に悩まされている場合は、無理に消そうとするより、専門家への相談をおすすめします。
まとめ
匂いで記憶が蘇るプルースト効果は、嗅覚がほかの五感とは異なり大脳辺縁系に直接情報を送ることで生まれる現象です。このメカニズムにより、匂いは記憶や感情と強く結びつき、私たちの日常生活に豊かな体験をもたらしています。
そして、プルースト効果の仕組みは、恋愛や勉強、医療・介護、ビジネスなどさまざまな場面で活用できます。弊社、プルーストでは香り印刷技術を用いて、印刷物に匂いを添えて相手に届けることが可能です。少しでも興味がありましたら、ぜひ下記ページからご覧ください。
香りの印刷所プルースト編集部
この記事は、香りの印刷所プルーストを運営している久保井インキ株式会社のプルースト編集部が企画・執筆した記事です。
香りの印刷所プルーストでは、香りの印刷をテーマにお役立ち情報の発信をしています。