お知らせ
【月別】季節の挨拶・時候の挨拶一覧|具体例や必要な理由・注意点を解説

季節の挨拶は、相手への気遣いを示すだけでなく、日本の美しい文化でもあります。しかし、手紙やビジネス文書を書くとき、「季節の挨拶をどう書けばいいのか分からない」と悩んだ経験はないでしょうか。
そこで今回は、月ごとに異なる季節の挨拶文例から使いわけのコツまで、初心者でもわかりやすく解説します。適切な季節の挨拶を使って、相手に良い印象を与える文書を作成する参考にしてください。
目次
季節の挨拶とは
季節の挨拶とは、手紙やはがきの冒頭で使う季節を表現した挨拶文のことです。旧暦では和風月名(わふうげつめい)という呼び名があります。「拝啓」などの頭語(とうご・手紙の最初に書く言葉)のあとに続けて書き、その時期の気候や自然の様子を表現するのが基本です。
「桜花の候」、「残暑お見舞い申し上げます」など、四季の美しさを言葉で表現し、相手への気遣いを示す日本独特の文化でもあります。 現代では、ビジネス文書から個人的な手紙まで幅広く使うようになっています。
季節の挨拶の種類
季節の挨拶には、格式の高い「漢語調」と親しみやすい「口語調」の2つの種類があります。相手との関係性や文書の性格によって使いわけるためにも、以下で紹介します。
漢語調
漢語調の季節の挨拶は、「○○の候」、「○○のみぎり」という形で表現する格式の高い文体です。主に、「初春の候」、「残暑の候」のように、短い言葉で季節を表現し、主にビジネス文書や改まった手紙で使用します。
言葉遣いが固く、礼儀正しい印象を与える書き方で、取引先や目上の人への文書に適しています。覚えやすく使いやすいのが特徴で、どの相手にも失礼にならない安全な表現を選びたいときにぴったりです。
口語調
口語調の季節の挨拶は、普段の話し言葉に近い自然で親しみやすい文体です。「桜の花が美しい季節となりました」、「暑い日が続いておりますが」のように、季節の様子を文章で表現します。
漢語調よりも身近で温かみがあり、親近感を演出できるため、個人的な関係の相手や親しい人への手紙に適しています。また、表現の自由度も漢語調よりも高く、書き手の個性を表現しやすい特徴もあります。
漢語調と口語調はどう使いわける?
漢語調と口語調は、届ける相手がどのような方であるかで使いわけます。主に、漢語調は「○○の候」という形式で格式が高く、ビジネス文書や改まった手紙に適しています。一方で、口語調は普段の話し言葉に近い表現で、親しい相手への個人的な手紙に向いた文体です。
具体的には、取引先、顧客、上司には漢語調を、家族、友人、知人には口語調を選ぶのが無難です。もし、迷った場合は漢語調を選んでおけばどのシーンでもまず失礼にはなりません。相手との距離感と文書の性格を考慮し、選択してください。
そもそも季節の挨拶が必要な3つの理由
手紙等を書こうと考えたとき、「普段から使う挨拶で良いのでは?」、「考えるのが面倒」と感じてしまう方もおられるはずです。ここからは、季節の挨拶がなぜ必要なのかの理由もお伝えします。
伝統的なマナーを守れる
まず季節の挨拶は、日本の伝統的な手紙文化の一部であり、マナーを守るために正しく使います。ご年配の方や格式を重んじる相手に対しては、季節の挨拶を省略すると失礼にあたる場合もあるからです。
日常生活において使う機会がなかったとしても、ビジネスや個人的な関係において、相手に敬意を示すために行う基本的なマナーとしての位置づけです。取引先にラフな普段着では行かないのと同じで、守るべきルールとして今もなお続いています。
相手への気遣いを表現できる
季節の挨拶を使えば、相手の健康や安全を気遣う気持ちを自然に伝えられます。たった一言、「寒さの厳しい折、お身体にお気をつけください」といったように、季節に応じた体調への配慮を示せば相手に対する思いやりが伝わります。
日本特有ともいえるこうした気遣いは、人間関係を良好に保つためにも必要となります。社交辞令であったとしても、そこに言葉があるだけで相手に「気にかけてくれている」と感じてもらえるのです。
文書に格式と品格を与える
季節の挨拶は上品で格式高い印象を与え、より目を通すべき文書であると伝える意味も込められます。特にビジネス文書では、相手企業からの信頼度を高め、今後の良好な関係を維持するための礼は尽くさなければなりません。
また、季節感のある美しい日本語を使えば、書き手の教養や文化的素養のアピールも可能です。相手に「きちんとした人」という印象を持ってもらい、今後も良い関係を築いていきたいのであればぜひ添えておきたいところです。
季節の挨拶を使う5つの場面

季節の挨拶を活用する場面は意外に多く、それぞれに適した表現があります。以下では、具体的によく記載する5つの場面を紹介します。
ビジネス文書
ビジネス文書では、取引先への報告書、提案書、契約書の送付状などで季節の挨拶を使います。 「拝啓 大暑の候、貴社のご隆盛を心よりお喜び申し上げます」のような格式高い表現で、相手企業への敬意を示すといった具合です。
四半期報告や年度はじめの挨拶状でも使えるため、長期的な取引関係の維持に貢献するビジネスマナーとしても役立ちます。なお、書き方で悩んだ際には上司や同僚に聞いておくと、これまでの慣習も同時に知る機会になります。
年賀状
新年を迎える年賀状でも使える「謹賀新年」も季節の挨拶ですし、「初春の候」といった言葉も添えられます。「新春を迎え、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます」のように、新年の喜びと相手への願いを表現しているケースもあります。
こうした挨拶は個人的な関係から業務上の関係まで幅広い相手に使え、1年の関係性を良好に保つ役割を果たします。古くから続く日本の伝統的なマナーであるため、よほど親しい仲でない限りはきちんと添えてください。
挨拶状
転職の際に用いる挨拶状でも、礼儀正しさを示すために季節の挨拶を使います。「拝啓 新緑の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます」のように書きはじめて、これまでの感謝の気持ちと新天地での抱負を伝えられます。
退職・転職の理由はさまざまですが、禍根を残さないためにもマナーとして覚えてください。関係者への印象を良好に保ったり、将来的なつながりを維持したりするなど、今後を過ごすためにも役立ちます。
お礼状
贈り物をいただいたり、お世話になったりした際のお礼状でも季節の挨拶を使います。「拝啓 紅葉の候、いかがお過ごしでしょうか」といった具合に丁寧に表現すると、感謝の気持ちをより伝えられるからです。
季節の移ろいとともに相手への感謝を伝えれば、心のこもった印象を与えます。また、個人的な関係を大切にし、継続的な良好な関係を築きたいと考えているその気持ちも相手に伝えられます。
暑中見舞い
定番ではありますが、夏の暑中見舞いでも「暑中お見舞い申し上げます」という季節の挨拶を使います。「連日の猛暑にもかかわらず、皆様にはお元気でお過ごしのことと存じます」といった言葉を添え、相手の健康を気遣えるとより良くなります。
親しい間柄であれば簡略化できますが、挨拶は会社で取引先に送るといったケースであれば年中行事でも必須です。夏の厳しい暑さを共有し、相手の体調を案じる気持ちをぜひ文字にして届けてください。
【月別】季節の挨拶の文例一覧
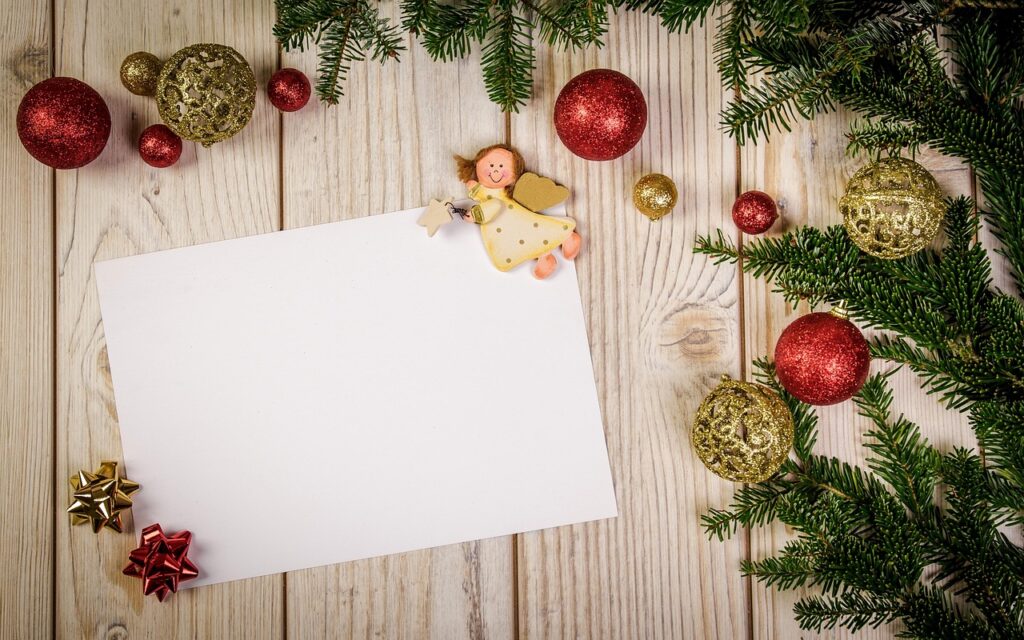
以下では、実際に書こうとして悩んだ方に向けて、月別にわけた季節の挨拶の文例を一覧で紹介しています。各月の上旬・中旬・下旬で適切な季節の挨拶を選びわけて、より正確で相手に響く挨拶文を作成する参考にしてください。
| 月 | 季節表現 | 挨拶例文 | 結びの例文 | 特徴・注意点 |
| 1月 | 新春・初春・寒冷 | 拝啓 新春の候、皆様におかれましてはお健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます | 本年もどうぞよろしくお願いいたします | 上旬は新年の喜び、中旬以降は寒さを表現。明るく前向きな印象を重視 |
| 2月 | 厳寒・立春・梅花 | 拝啓 厳寒の候、皆様にはお変わりなくお過ごしのことと存じます | まだまだ寒い日が続きますが、お身体にお気をつけください | 一年でもっとも寒い時期。上旬は寒さ、中旬以降は春の兆しを表現 |
| 3月 | 早春・春暖・桃花 | 拝啓 早春の候、春の訪れと共に皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます | 春とはいえ、まだまだ寒暖の差が激しい季節です。お身体にお気をつけください | 卒業・転職など人生の節目。新たなスタートへの願いを込める |
| 4月 | 桜花・陽春・春爛漫 | 拝啓 桜花の候、皆様におかれましてはお元気でお過ごしのこととお慶び申し上げます | 新年度を迎え、お忙しい毎日かと存じますが、お身体にお気をつけください | 桜の美しさと新年度のはじまり。希望に満ちた表現が適している |
| 5月 | 新緑・立夏・薫風 | 拝啓 新緑の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます | 過ごしやすい季節ではございますが、くれぐれもお身体にお気をつけください | 新緑の爽やかさ。ゴールデンウィークへの言及も効果的 |
| 6月 | 梅雨・入梅・紫陽花 | 拝啓 入梅の候、鬱陶しい梅雨空が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか | 梅雨明けまでもう少しの辛抱です。どうぞお身体にお気をつけください | 湿気や雨による体調への配慮が重要。雨の季節の情緒も表現 |
| 7月 | 盛夏・大暑・炎暑 | 拝啓 盛夏の候、連日の暑さにもかかわらず、皆様にはお元気でお過ごしのこととお慶び申し上げます | 暑さも本格的になってまいります。どうぞお身体にお気をつけください | 夏本番の暑さと梅雨明けの開放感。熱中症への注意を促す |
| 8月 | 猛暑・残暑・晩夏 | 拝啓 残暑の候、厳しい暑さが続いておりますが、お元気でお過ごしでしょうか | まだまだ暑い日が続きそうです。くれぐれもお身体にお気をつけください | もっとも暑い時期。お盆休みへの言及も可。体調管理への配慮を強調 |
| 9月 | 初秋・新涼・秋風 | 拝啓 初秋の候、朝夕には涼しい風を感じる季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか | 季節の変わり目でございます。どうぞお身体にお気をつけください | 暑さから涼しさへの変化。寒暖差への注意が必要 |
| 10月 | 秋涼・紅葉・秋晴れ | 拝啓 秋涼の候、さわやかな秋晴れの日が続いておりますが、皆様にはお元気でお過ごしのこととお慶び申し上げます | 朝夕の冷え込みも感じられるようになりました。風邪など召されませんようお気をつけください | 過ごしやすい美しい季節。スポーツや読書の秋としての要素も |
| 11月 | 晩秋・向寒・霜月 | 拝啓 晩秋の候、朝夕の冷え込みも厳しくなってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか | これから寒さも本格的になってまいります。お風邪など召されませんようお気をつけください | 晩秋から初冬への移り変わり。紅葉の美しさや収穫の喜びも |
| 12月 | 師走・歳末・初冬 | 拝啓 師走の候、何かとお忙しい毎日をお過ごしのこととお察しいたします | 寒さも厳しくなってまいります。良いお年をお迎えください | 年末の慌ただしさ。一年の感謝と来年への期待を表現 |
なお、ビジネス用途では丁寧語を基本とし、気候の違いにより表現を調整してください。気候変動により従来の季節感と異なる場合は、実際の気候に合わせて柔軟に対応できればより相手へ気持ちを伝えられます。
季節の挨拶の正しい書き方を5つのステップで解説
どのように書くのかがわかっても、実際にすぐ書き出してしまうと失礼にあたる表現を使ってしまいかねません。以下では基本となるステップにわけて正しい季節の挨拶を書くための方法を紹介します。
1. 手紙を送る時期を確認する
まず、書き手がいま感じている季節ではなく、手紙やはがきが相手に届く時期を正確に調べて内容を決めるのがスタート地点です。郵送にかかる日数も考慮して、実際に相手が読む時期に適した季節の挨拶を選ぶためです。
例えば、3月29日に投函して4月1日に届く場合は、4月の季節の挨拶を使うのが適切です。また、地域による気候の違いも考慮し、相手の住んでいる場所の季節感に合わせればより気持ちを込められます。
2. 相手との関係性を整理する
次に、相手との関係性を整理し、相手をよく知っているのであれば、年齢や立場の違いも考慮できる状態を目指します。目上の方には特に丁寧な表現を心がけたり、初対面の相手には無難な表現を選んだりできるためです。
- 年齢、役職、立場、関係の長さ(初対面・取引歴・長年の付き合いなど)を整理する
- 上司・顧客・同僚・後輩など、自分に対してどのような立場にあるかを明確にする
- ビジネスメール、カジュアルなチャット、面談、プレゼンなどの状況を考える
- 相手の好みや過去のやり取りを反映する
長年の付き合いがある相手には、少し個性を出した表現を選ぶといった方法も取れます。いつも同じ定型文を送るのではなく、あなたを知ってもらう意図で工夫するためにも相手の情報は丁寧に整理してください。
3. 漢語調か口語調かを決める
文書の性格と先に整理した相手との関係を考慮して、漢語調と口語調のどちらを使うかを決定します。基本は、ビジネス関係なら漢語調の格式高い表現、親しい友人なら口語調の親しみやすい表現です。
具体的には、ビジネス文書、公的な挨拶状、改まった場面では漢語調が適しており、個人的な手紙、親しい関係の相手、カジュアルな場面では口語調を選びます。繰り返しとなりますが、迷った場合は漢語調を選んでおけば失礼にはなりません。
4. 具体的な季語を選ぶ
ステップ1で調べた時期と文体に合わせて、月の上旬、中旬、下旬による季語を選びます。例えば、4月上旬なら「桜花の候」、4月下旬なら「晩春の候」のように使いわけるといった具合です。
- 1月:新春・初春 ― 新春の候、本年もよろしくお願いいたします。
- 2月:厳寒・立春 ― 厳寒の候、どうぞご自愛ください。
- 3月:早春・春暖 ― 早春の候、体調にお気をつけください。
- 4月:桜花・陽春 ― 桜花の候、新年度もご活躍をお祈りいたします。
- 5月:新緑・薫風 ― 新緑の候、爽やかな季節をお楽しみください。
- 6月:梅雨・紫陽花 ― 入梅の候、体調を崩されませんように。
- 7月:盛夏・大暑 ― 盛夏の候、暑さにご自愛ください。
- 8月:残暑・晩夏 ― 残暑の候、まだまだ暑さにお気をつけください。
- 9月:初秋・秋風 ― 初秋の候、季節の変わり目にご注意ください。
- 10月:秋涼・紅葉 ― 秋涼の候、さわやかな秋をお過ごしください。
- 11月:晩秋・向寒 ― 晩秋の候、寒さに向かう折ご自愛ください。
- 12月:師走・歳末 ― 師走の候、良いお年をお迎えください。
上記を例にその年の実際の気候状況も考慮し、早い桜の開花や遅い梅雨入りなどの現実に合わせた調整も考えてください。「新春の候」、「晩夏の候」など難しくない表現であれば、取り入れやすいはずです。
5. 結びの挨拶とセットで完成させる
書き出しの季節の挨拶を決めたら、それに対応する結びの挨拶も同時に考えておきます。書き出しと結びで一貫した季節感を保ち、相手への配慮を表現するためです。また、全体のバランスを考えて、読み手にとって心地よい流れを作る際にも役立ちます。
例えば、書き出しで暑さを表現したなら、結びでも暑さ対策への気遣いを示してください。頭語と結語の組み合わせも確認し、「拝啓」なら「敬具」で締めくくるというマナーが基本です。
【関連記事】手紙・便箋に香りづけする方法-匂いをつけて想いを届けるには
季節の挨拶で失敗しないための注意点
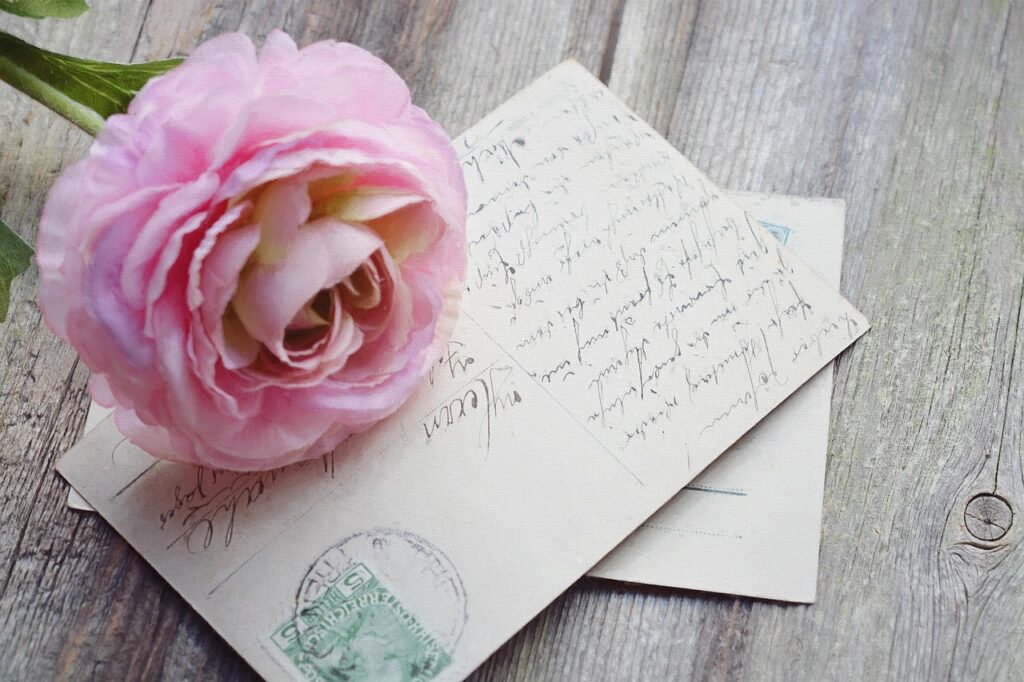
季節の挨拶で失敗しないためにも、書く際に知っておきたい注意点は以下のとおりです。意外に見落としやすい点があるため、ぜひ参考にしてください。
実際の気候と合わせる
繰り返しお伝えしていますが、季節の挨拶を選ぶ際は、その年の実際の気候状況と合わせてください。例えば、異常に暑い春に「春寒の候」を使ったり、暖冬の年に「厳寒の候」を使ったりすると、読み手に違和感を与えてしまいます。
天気予報や気象情報をチェックし、現実の気候に即した表現を選べば、より自然で共感を得られる季節の挨拶となります。相手も「確かにその通りだ」と感じ、書き手の気遣いと観察力を評価してもらいやすいです。
地域差を考える
見落としてしまいやすいのが、日本は南北に長い国土を持つため、同じ時期でも地域によって気候が異なる点です。例えば、北海道の3月はまだ雪が残る冬の様相ですが、沖縄の3月は既に初夏の陽気になるといった違いがあります。
相手の住んでいる地域の気候を考慮して、その地域に適した季節の挨拶を選んでください。全国一律の表現ではなく、相手の実際の体験に即した表現を使えば、より心のこもった挨拶となり、地域への理解と配慮を示せます。
時期のズレに気をつける
手紙やはがきを書く日と、相手に届く日との間にはタイムラグがあります。郵送日数を考慮せずに季節の挨拶を選ぶと、届いた時には季節が変わっているという失敗を引き起こしやすいです。
特に季節の変わり目には注意が必要で、3月末に書いて4月に届く場合は4月の挨拶を使わなくてはなりません。投函日ではなく、相手が読む日を基準に季節の挨拶を選ぶというルールを常に頭に入れてください。
頭語と結語の組み合わせを確認する
季節の挨拶を使う際は、頭語と結語の正しい組み合わせを必ず確認してください。「拝啓」ではじめたら「敬具」で終わる、「謹啓」ではじめたら「謹白」で終わるなど、決められた組み合わせはいくつもあります。
細かく調べて書き上げたとしても、間違った組み合わせがせっかくの丁寧な季節の挨拶を台なしにしてしまいます。なお、「前略」を使ったのであれば、季節の挨拶を省略しても構いません。
香り印刷で挨拶にさらに季節感を出せる
ここまで、季節の挨拶をお伝えしてきましたが、どれだけ丁寧に書いても相手に残る印象はほかの方とは差別化できません。そこでおすすめしたいのが、相手に届くタイミングを意識した香りを添える方法です。
例えば、香り印刷を使った季節の挨拶状は嗅覚からも季節感を伝えられ、受け取った相手により強い印象を残せます。春の挨拶状には桜の香り、夏の暑中見舞いには爽やかなミントの香りを付けるだけで、言葉では表現できない季節の魅力を伝えるのです。
ビジネスではより相手への印象を強めて、営業での反応率を高めるといった工夫を凝らすはずです。その際、香りを添えれば、特別な挨拶状に仕上がります。
【関連記事】手紙やDMの開封率を向上する方法|香り印刷の新たなアプローチ
香り印刷はプルーストへ
香り印刷所プルーストでは、季節の挨拶状に最適な香り付きハガキ・ポストカードをご用意しています。14種類の厳選した香りのなかから、季節に応じた香りを選べば、文字だけでは伝えきれない季節感と心遣いを表現できます。
具体的には、「ぎゅっとしぼる鮮烈レモン」や「一粒のミントタブレット」で夏の爽やかさを、「沸きたつ芳醇ローズ」や「清楚なラベンダーブーケ」で春の美しさを演出するなどです。香りの保証期間は出荷日より6か月間と長持ちしますし、擦らなくてもほのかに香り、擦るとより香りが強くなる仕組みです。
季節の手紙に関するよくある質問(FAQ)
最後に、季節の挨拶についてよくある疑問にお答えします。
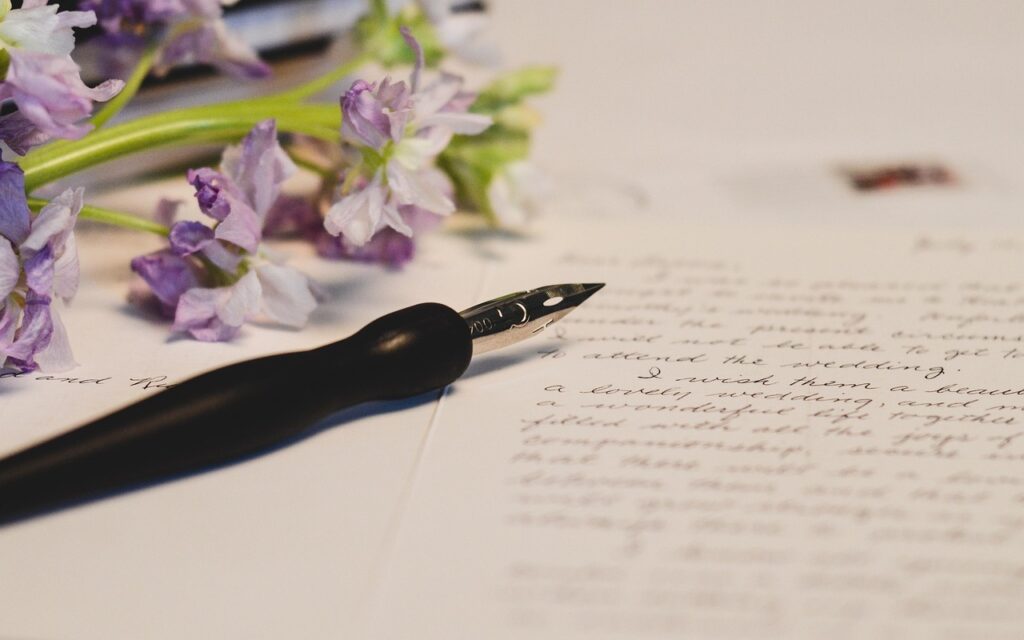
季節を問わず使える表現は?
季節を問わず使える表現は、「時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」といった、特定の季節に関する内容を含まない挨拶表現があります。季節の判断に迷った場合や、年間を通じて使用する定型文書では、このような表現が便利です。
ただし、季節感がない分、やや形式的で冷たい印象を与えやすいのも事実です。緊急性の高い文書や、季節の挨拶を考える時間がない場合の代替手段として使えますが、可能な限り季節に応じた挨拶を使用するほうが、相手への気遣いと文書の品格を高められます。
季節のあいさつの例文は?
季節の挨拶の例文は月ごとに異なり、1月なら「新春の候、皆様お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます」、7月なら「盛夏の候、連日の暑さにもかかわらず、皆様にはお元気でお過ごしのこととお慶び申し上げます」などがあります。
漢語調と口語調の2種類があり、相手との関係性によって使いわけてください。ビジネス文書には格式高い漢語調を、親しい関係には親しみやすい口語調を選ぶのが無難です。
手紙の書き出しに季節の挨拶を書くのはなぜですか?
季節の挨拶を書く理由は、相手への気遣いと敬意を表現するためです。日本の伝統的な手紙文化では、季節の移ろいを共有し、相手の健康や幸福を願う気持ちを表現するマナーが古くから守られてきました。
また、文書に品格と格式を与え、書き手の教養や礼儀正しさを示す効果もあります。現代でも、相手との良好な関係を築き、維持するためのコミュニケーション手段としての位置づけであり、日本社会における基本的なマナーとして定着しています。
まとめ
季節の挨拶は、日本の美しい文化であり、相手への気遣いを表現するコミュニケーション手段です。月ごとに定められた時候の挨拶を、相手との関係性や文書の性格に応じて漢語調(格式高い)・口語調(親しみやすい)から適切に選択し、書き出しと結びをセットで使う点に留意してください。
実際の気候や地域差、タイミングに注意を払い、頭語と結語の組み合わせも正しく使用できれば、相手へ強く印象を残せる季節の挨拶に仕上がります。もし、少しでも印象を強めたいのであれば、香り印刷もぜひご検討ください。
香りは嗅覚を刺激し、記憶に深く刻まれやすいという特性があります。興味があれば、ぜひ下記ページから製品の一覧をぜひご覧ください。
香りの印刷所プルースト編集部
この記事は、香りの印刷所プルーストを運営している久保井インキ株式会社のプルースト編集部が企画・執筆した記事です。
香りの印刷所プルーストでは、香りの印刷をテーマにお役立ち情報の発信をしています。









