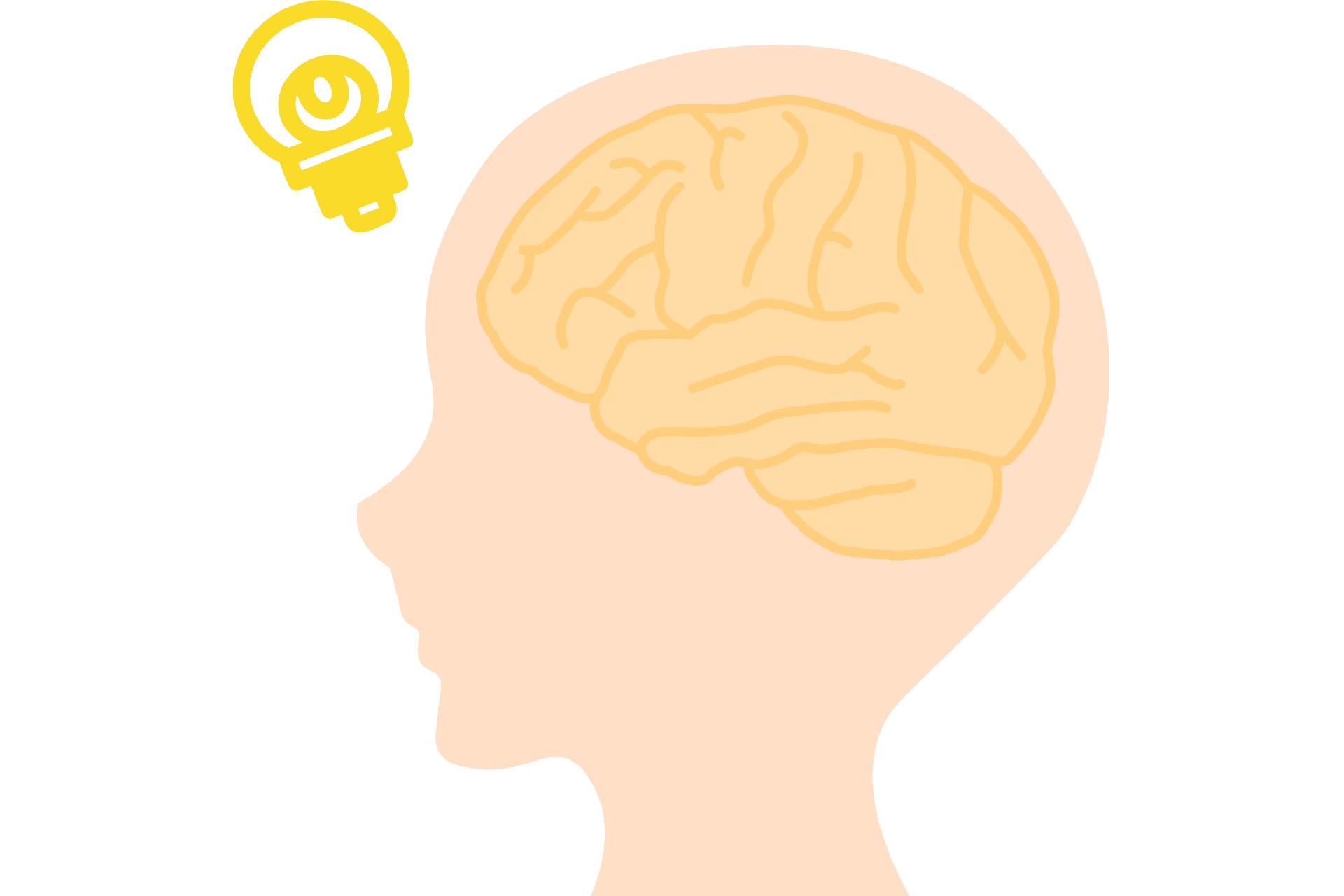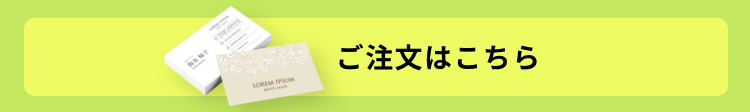コラム
精油とアロマオイルの違いとは?7つの使い方と注意点まで徹底解説

精油とアロマオイル、名前は似ていますが、実はまったく異なるものです。この違いを正しく理解することで、ビジネスシーン・個人利用のいずれでも、目的に合った製品選びができます。
この記事では、精油とアロマオイルの違いから、ビジネスにも活用できる使い方、購入時のチェックポイントまで解説します。香りの持つ力を活用するための第一歩として、まずはこの基本的な違いを押さえておきましょう。
香りのある暮らしを始めたい方、ビジネスに香りを取り入れたい方、ぜひ参考にしてみてください。
Index
精油とアロマオイルの違い
精油とアロマオイルの違いは、「原材料か」、「加工品か」にあります。例えるなら、精油は「果物を絞った100%ジュース」、アロマオイルは「果汁入り飲料」や「フレーバー飲料」のような違いがあります。
精油は植物から抽出された100%天然の香り成分で、アロマテラピーの基本となる高濃度の芳香物質です。そのため、「植物から取れた原液そのもの」となります。
一方で、アロマオイルは精油を希釈したものや、合成香料を含む場合もある香りを楽しむためのオイルです。「精油を薄めたもの」または「人工的な香りを含む製品」となります。
精油(エッセンシャルオイル)とは
精油は、植物の花、葉、果皮、果実、心材、根、種子、樹皮、樹脂などから抽出した天然素材です。英語では「エッセンシャルオイル(Essential Oil)」と呼ばれています。有効成分を高濃度に含有した揮発性の芳香物質で、各植物によって特有の香りと機能を持っています。
ラベンダーやローズ、ユーカリなどさまざまな種類があり、それぞれがリラックス効果や集中力向上、気分転換など異なる効果が期待できます。高品質な精油は純度が高く、少量でも強い香りと効果を発揮するのが特徴です。
アロマオイルとは
アロマオイルは、香りを楽しむことを主な目的としたオイル製品です。精油を希釈したものから、合成香料を含むものまで幅広い種類があります。一般的には精油をキャリアオイル(植物油)で薄めたものや、合成香料と植物油を混ぜたものを指します。
アロマオイルは精油に比べて価格が手頃で、香りも穏やかなため、日常的に使いやすいという特徴があります。ただし、合成香料を含む場合は、天然の精油のような複雑な香りや療法的効果は期待できません。
【関連記事】【ビジネス向け】アロマの香りの選び方は?取り入れ方も解説
精油とアロマオイルの製造方法の違い

精油は植物から直接抽出される天然素材で、主に水蒸気蒸留法や圧搾法で製造されます。一方、アロマオイルは精油をベースに作られるものや、合成香料から作られるものがあり、製造工程が異なります。
精油の製造には大量の植物原料が必要で、例えばローズ精油1kgには約3〜5トンのバラの花が必要です。この希少性が精油の高価格の理由でもあります。
対照的に、アロマオイルの製造は比較的シンプルで、合成香料やキャリアオイルを混ぜるだけの場合もあります。そのため、コストが抑えられ、大量生産も容易なのです。
参照:AEAJ | 精油とは
精油・アロマオイルの7つの使い方
精油・アロマオイルには、ビジネスシーンから日常生活まで、目的に合わせたさまざまな活用方法があります。以下で、代表的な7つの使い方を紹介します。
アロマディフューザーを使う
精油・アロマオイルのもっとも一般的な使い方で、専用のディフューザーを使って香りを拡散する方法です。水を入れたディフューザーに精油を数滴(通常3〜5滴)垂らして使用します。超音波式、ネブライザー式、加熱式などさまざまなタイプのディフューザーがあります。
部屋全体に香りが広がり、リラックスや集中力アップなどの効果が期待できます。オフィスでは会議室や受付エリアなど、来客対応の場所に設置すると、好印象を与えることができるでしょう。
お風呂に数滴垂らす
湯船に精油・アロマオイルを2〜3滴垂らして、香りと効果を楽しむ方法です。湯気と一緒に香りが広がり、全身で香りを感じられます。温浴効果と精油の効果が相乗的に働き、リラックス効果が高まります。
精油は水に溶けないので、入浴剤や塩、はちみつなどと混ぜると分散しやすくなります。肌に直接触れるため、敏感肌の人は少量から試すのが安全です。仕事で疲れた日の帰宅後のリラックスタイムに最適で、翌日のパフォーマンス向上にも役立ちます。
キャリアオイルで希釈してマッサージに使用する
精油をキャリアオイル(植物油)で希釈して、マッサージオイルとして使用する方法です。肌に直接塗布するため、必ず希釈することが重要で、一般的な希釈率は1〜3%(キャリアオイル10mlに対して精油2〜6滴程度)となります。
香りの効果と、皮膚からの吸収による効果の両方が期待できます。部分マッサージ(首、肩、手など)・全身マッサージにも活用できます。デスクワークで凝り固まった肩や首のマッサージに使えば、仕事の効率アップにもつながるでしょう。
ハンカチに垂らして携帯する
ハンカチやコットン、マスクの内側などに精油・エッセンシャルオイルを1〜2滴垂らして持ち歩く方法です。外出先でも手軽に香りを楽しめる、シンプルで便利な使い方です。気分転換やリフレッシュしたいとき、集中したいときなどに活用できます。
精油の種類によって、目的別に使いわけられるのも魅力です。例えば、重要なプレゼンテーション前にはローズマリーの香りで集中力を高めたり、緊張する商談前にはラベンダーでリラックスしたりといった使い方ができます。
アロマスプレーを手作りする
精油と水、無水エタノールを混ぜて作る手作りスプレーです。部屋の消臭や空気清浄、寝具やカーテンの香り付けに便利な方法となります。基本的な作り方は、無水エタノール10mlに精油10〜20滴を溶かし、精製水90mlを加えるだけです。
アロマオイルであればそのまま使えるため、さまざまな効果が期待できます。手作りなので、自分好みの香りや濃さに調整できるのも魅力です。
アロマストーンに染み込ませる
素焼きの専用ストーンに精油・アロマオイルを数滴垂らして香りを楽しむ方法です。電気を使わず、静かに香りを楽しめることから、小さな空間(玄関、トイレ、クローゼットなど)での使用に適しています。
精油であれば3〜5滴垂らすだけで、数日間香りが持続します。香りが弱くなったら追加で垂らすことで、繰り返し使用可能です。デスク周りに置けば、静かに香りが広がり、周囲に迷惑をかけることなく香りの効果を得られます。
香り印刷でビジネスに取り入れる
香り印刷とは、印刷物に香りを付加する技術のことです。精油やアロマオイルとは若干異なりますが、名刺やパンフレット、DMなどに香りを付けることで、強い印象を与え、記憶に残るコミュニケーションが可能になります。
香り印刷所プルーストでは、「プルースト効果」(香りによって記憶や感情が呼び起こされる現象)を活用した印刷サービスを提供しています。相手に強い印象を与え、記憶に残りやすいため、ビジネスでの差別化に有効です。
ビジネスに香りの力を取り入れたい方は、ぜひ香り印刷所プルーストにご相談ください。14種類の厳選された香りから、ブランドイメージに合った香りをお選びいただけます。
【関連記事】香り印刷とは?こすると匂いがする仕組みから製品例まで完全解説
精油・アロマオイルを購入する時の5つのチェックリスト

精油やアロマオイルを購入する際は、品質や効果を確保するために以下のポイントをチェックしましょう。日常からビジネスでの活用を考える場合は、品質の良いものを選ぶことが重要です。
成分表示を必ず確認する
本物の精油は、100%天然の植物から抽出されたものです。ラベルに「100% Pure」「Pure Essential Oil」などの表記があるか確認しましょう。また、合成香料や添加物が含まれていないことも重要です。
一方で、「香料」「フレグランスオイル」という表示がある場合は、合成香料を含むのが一般的です。加えて、品質の良い精油は、ボトルのラベルに植物の和名と学名(ラテン名)が明記されています。学名があることで、どの種類の植物から抽出されたのかが明確になります。
有効成分を含有量を見る
アロマオイルではなく、精油の場合のみに確認したいのが有効成分の含有量です。精油は植物の有効成分を高濃度に含んでいるため、少量でも効果を発揮します。一般的に、精油1滴には約20mg〜25mgの有効成分が含まれているそうです。
この高濃度さゆえに、原液での使用は避け、適切に希釈して使うことが基本です。高濃度であるため、香りが強く、長持ちするのが特徴です。日常やビジネスでの活用を考える場合、この高濃度さが香りの演出につながります。
使用目的に合った香りを選ぶ
アロマオイルを選ぶ際は、何のために使うのかという目的を明確にすることが大切です。リラックス、集中力アップ、気分転換など、目的によって適した香りが異なります。
香りの好みも重要で、どれだけ効果があっても好きでない香りは長続きしません。初めての場合は、万人受けする柑橘系やラベンダーなどから始めるのがおすすめです。可能であれば購入前に香りをテストできるショップを利用すると良いでしょう。
信頼できるブランドかを見る
アロマオイルは品質にばらつきがあるため、信頼できるブランドから購入することをおすすめします。長年の実績があり、品質管理がしっかりしているブランドを選ぶと安心です。
製造方法や原料の調達方法を公開しているブランドは透明性が高く信頼できます。口コミやレビューも参考になりますが、個人差があることを念頭に置きましょう。専門店やオーガニックショップなど、専門知識を持ったスタッフがいる店舗での購入もおすすめです。
保存方法を確認する
精油や、精油を原料としたアロマオイルは光、熱、酸素に弱く、適切な保存をしないと品質が劣化します。遮光瓶(茶色や青色のガラス瓶)に入っているのは、光から精油を守るためです。
冷暗所での保存が基本で、直射日光や高温は避けるべきです。開封後は酸化が進むため、キャップをしっかり閉めて空気に触れる時間を最小限にしましょう。適切に保存すれば、種類にもよりますが一般的に1〜3年は品質を保てます。
精油・アロマオイルを使うときの5つの注意点

精油やアロマオイルを安全に使用するためには、以下の注意点を守ることが大切です。個人やビジネスで導入する場合は、関係者全員の安全を考える必要があります。
原液を直接肌につけない
アロマオイルよりも精油は高濃度なため、原液のまま直接肌につけるとかぶれや炎症を起こす可能性があります。肌に使用する場合は、必ずキャリアオイル(植物油)で希釈することが基本です。
一般的な希釈率は1〜3%(キャリアオイル10mlに対して精油2〜6滴程度)です。顔や敏感な部位に使用する場合は、さらに低濃度(0.5〜1%)に希釈しましょう。
合成香料を含むアロマオイルは、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。肌につけると、かぶれや発疹、かゆみなどの症状が出ることもあるため、パッチテスト(少量を腕の内側などに塗って反応を見る)を行うと安心です。
妊娠中や授乳中は専門家に相談する
妊娠中や授乳中は、ホルモンバランスの変化や胎児への影響を考慮して精油の使用に注意が必要です。一部では使えますが、妊娠初期(最初の3か月間)は、精油・アロマオイルの使用を避けるべきとされています。
クラリセージ、ジャスミン、ローズマリーなど、子宮を刺激する可能性のある精油は注意が必要です。使用する場合は、必ずアロマテラピーの専門家や医師に相談しましょう。
安全とされる精油でも、通常より低濃度で使用するのが基本です。職場で香りを取り入れる場合は、妊娠中の従業員や来客への配慮も必要です。
ペットがいる環境での使用に注意する
犬や猫などのペットは人間より嗅覚が敏感で、精油・アロマオイルの成分に対する反応も異なります。例えば、猫は肝臓で解毒する能力が弱く、一部の精油に含まれる成分が毒性を持つこともあるためです。
ティーツリー、ユーカリ、シトラス系など、ペットにとって有害な精油もあるため注意が必要です。ディフューザーを使用する場合は、ペットが自由に出入りできる別の部屋を用意しましょう。
ペットに直接精油を使用したり、舐められる可能性のある場所に使用したりするのは避けるべきです。ペットを同伴できるオフィスや自宅では、この点に注意が必要です。
光や熱から遠ざけて保存する
精油・アロマオイルは光、熱、酸素に弱く、これらに長時間さらされると品質が劣化します。遮光瓶(茶色や青色のガラス瓶)に入れ、直射日光の当たらない冷暗所で保存するのが基本です。
冷蔵庫での保存は必要なく、むしろ出し入れの温度差で劣化が早まる可能性もあります。キャップはしっかり閉め、空気に触れる時間を最小限にしましょう。適切に保存すれば、精油の種類にもよりますが一般的に1〜3年は品質を保てます。
子どもの手の届かない場所に保管する
アロマオイルのなかでも精油は高濃度の成分を含むため、誤飲や誤用による事故を防ぐために子どもの手の届かない場所に保管する必要があります。見た目や香りから飲み物と間違えられる可能性があり、誤飲すると健康被害の恐れがあります。
柑橘系の精油は、飲み物のような爽やかな香りがするため注意が必要です。子どもが使用する場合は、必ず大人の監督のもとで適切に希釈したものを使用しましょう。
万が一誤飲した場合は、無理に吐かせず、すぐに医師に相談してください。子どもが訪れる可能性のあるオフィスや店舗では、この点に注意が必要です。
まとめ
精油とアロマオイルの違いを理解し、適切な使い方を知ることで、香りの持つ力を最大限に活用できます。ビジネスシーンでは、香りによる記憶の定着や感情への働きかけが、他社との差別化につながります。
香り印刷所プルーストでは、名刺やDM、パンフレットに香りを付け、お客様の記憶に残る「プルースト効果」を活用した香り印刷サービスを提供しています。14種類の厳選された香りから、ブランドイメージに合った香りをお選びいただけますので、ビジネスに香りの力を取り入れたいとお考えの方は、ぜひ香り印刷所プルーストにご相談ください。
香りの印刷所プルースト編集部
この記事は、香りの印刷所プルーストを運営している久保井インキ株式会社のプルースト編集部が企画・執筆した記事です。
香りの印刷所プルーストでは、香りの印刷をテーマにお役立ち情報の発信をしています。