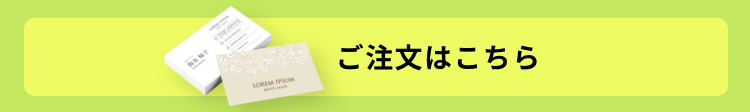コラム
飲食店のマーケティングはどうする?必要な5つの理由とおすすめの手法を解説

飲食業界は年々競争が激化し、美味しい料理やサービスだけでは選ばれる店になることが難しくなっています。日本には約70万店舗の飲食店があり、同じエリア内でも多くの競合店があります。このような環境で生き残るためには、戦略的なマーケティングが欠かせません。
そこで今回は、飲食店のマーケティングが必要な理由から具体的な手法まで、実践的な情報を紹介します。競争が激しい市場でも独自のポジションを確立し、安定した経営を実現する参考にしてください。
Index
飲食店のマーケティングとは
飲食店のマーケティングとは、「お客様のニーズを理解し、それに応える価値を提供することで、継続的な集客と売上を実現する活動」のことです。単なる宣伝や広告ではなく、市場調査、商品開発、集客、顧客管理までを含む総合的な取り組みとなります。
わかりやすくすると、「売れる仕組みづくり」として、顧客が「あのお店に行きたい」「あのお店の〇〇を食べたい」と思ってもらえるような戦略を立てるということです。
なお、マーケティングと集客の違いは、集客がマーケティングの一部であるという点にあります。集客は「人を集める」活動ですが、飲食店マーケティングは単に人を集めるだけでなく、顧客満足度を高め、リピーターを増やし、持続的な利益を生み出すための包括的な取り組みです。
飲食店にマーケティングが必要な5つの理由

飲食業界は競争が激しく、美味しい料理やサービスだけでは生き残れない時代になっています。マーケティングを行い、お店の強みを最大限に活かし、顧客に伝えることが可能になります。
競争の激化に対応できる
日本には2023年時点で約80万店舗の飲食店が存在し、同じエリア内でも多数の競合店がひしめいている状況です。新店舗のオープンと閉店が頻繁に起こる「浮き沈みの激しい業界」であるため、競争を勝ち抜く戦略が必要です。
飲食店マーケティングであれば、競合店との違いを明確にし、顧客に選ばれる理由を作り出せます。
競争が激化する中で、マーケティングを行わないと「なぜこの店を選ぶべきか」という顧客の疑問に答えられません。飲食店マーケティングは激しい競争環境の中で生き残るための必須スキルなのです。
参照: Circana Japan |外食・中食 調査レポート
顧客ニーズの多様化に応える
現代の消費者は多様なニーズを持ち、「インスタ映え」「健康志向」「地産地消」「ベジタリアン対応」などさまざまな価値観で店舗を選ぶ傾向があります。マーケティングを通じて顧客の声を集め、分析することで、こうした多様なニーズを把握できます。
飲食店マーケティングでは、顧客データを活用して潜在的なニーズも発見可能です。デリバリー・テイクアウトニーズへの対応、アレルギー対応や特定食材不使用への要望なども把握できるでしょう。ニーズの変化を先取りすることで、他店に先駆けて新しいサービスを提供し、競争優位性を確保できます。
集客力を高められる
飲食店マーケティングを実践することで、新規顧客の獲得とリピーターの増加が期待できます。SNS、ホームページ、グルメサイト、チラシなど複数の手段を組み合わせて、より広い層に店舗の魅力を伝えられるためです。
ターゲットを明確にしたマーケティングは、費用対効果の高い集客を実現します。集客力の向上は直接的な売上増加につながるだけでなく、口コミの連鎖による相乗効果も期待できます。
リピーター獲得につながる
新規顧客の獲得は、既存客の維持より5倍のコストがかかる(1:5の法則)と言われており、リピーターの獲得は経営効率化の鍵です。この点、飲食店マーケティングでは顧客データを活用したCRM(顧客関係管理)により、来店頻度や好みに合わせたアプローチが可能です。
また、リピーターは口コミの発信源となり、新規顧客獲得にも貢献する好循環を生み出します。既存客の離れる割合を5%改善できると、利益率は25%の改善が期待できる、この5:25の法則も意識してください。
店舗の差別化が図れる
似たようなコンセプトや料理を提供する店舗が多い中、マーケティングによって独自の強みを打ち出せます。飲食店マーケティングでは、商品、価格、場所、販促、人などの要素を組み合わせて独自のポジショニングを確立するからです。
差別化されたブランドイメージは、顧客の記憶に残りやすく、選ばれる理由となります。飲食店マーケティングは「なぜこの店を選ぶべきか」という明確な理由を作り出し、競合との差別化を実現する戦略なのです。
飲食店のマーケティングの基本となる4つの要素
飲食店マーケティングの基本は「4P」と呼ばれる4つの要素から成り立っています。
4Pとは「Product(商品)」「Price(価格)」「Place(場所)」「Promotion(販促)」の頭文字です。この要素をバランスよく組み合わせて、マーケティング戦略を構築できます。
商品(メニュー開発・品質管理)
飲食店マーケティングにおける「商品」は、提供する料理やドリンクだけでなく、サービスの質や店舗の雰囲気も含む総合的な体験です。メニュー開発では、ターゲット顧客の好みや価格帯、季節性、トレンドなどを考えることが重要です。
品質管理は顧客満足度に直結し、一貫した味やサービスの提供が信頼構築につながります。「お客にとって価値がある料理」を提供することがマーケティングの第一歩であり、「突き抜けた料理」を創造することが差別化につながるのです。
価格(客単価・原価管理)
飲食店マーケティングにおける「価格」は、顧客が感じる価値と実際の価格のバランスが重要です。適切な価格設定は、顧客の購買行動やブランドイメージ、利益率に影響します。
この場合、原価率と利益率のバランスを考慮しながら、競合店との価格差も意識した戦略が必要です。価格は一度決めたら固定ではなく、季節やトレンド、経済状況など外部環境の変化に応じて見直すことも検討の余地があります。
場所(立地特性)
飲食店マーケティングにおける「場所」は、立地条件が集客や売上に直結する要素です。駅前、オフィス街、住宅地など立地によって客層や来店時間帯が異なるため、それに合わせた戦略が必要です。
立地は経営途中で変更が難しいため、出店前の商圏分析を行います。商圏の人口動態や競合店の状況、人の流れなどを分析し、その立地に最適な業態やメニュー構成を検討することが成功の鍵です。
販促(情報発信・集客施策)
飲食店マーケティングにおける「販促」は、店舗の魅力を顧客に伝え、来店を促すための活動です。デジタル(SNS、ホームページ、グルメサイト)とアナログ(チラシ、看板、イベント)の両方をバランスよく活用することが有効です。
ターゲット顧客に合わせた販促手段の選択が重要で、若年層にはSNS、シニア層には紙媒体など使いわけましょう。「あらゆる手段を使って告知をする」ことがマーケティングの第2ステップです。
しかし、世の飲食店が告知を十分にせず、集客できていない現状があります。ターゲットに合わせた情報発信と来店動機の創出を通じて、認知拡大と売上向上を実現するものだと考えましょう。
【関連記事】香り×販促で売上UP!得られる効果と取り入れる5つの方法
飲食店のマーケティングで押さえるべき7つのポイント

飲食店マーケティングを実践するためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。以下に、意識すべき7つのポイントを紹介します。
ターゲット層を明確にする
飲食店マーケティングでは「だれに向けて」サービスを提供するかを明確にすることが最初のステップです。ターゲットを絞ることで、メニュー開発やサービス内容、価格設定、販促方法などすべての施策が一貫性を持つようになります。
「できるだけ人に来てほしい」という考えは、結果的にだれにも刺さらない中途半端な店になるリスクがあります。ターゲットを明確にすることで、限られた経営資源(時間、人材、資金)を効率的に投下できます。
競合との差別化を図る
飲食店マーケティングでは、同じエリアや同じジャンルの競合店との違いを明確にしてください。差別化ポイントがなければ、顧客は価格や立地だけで店舗を選ぶことになり、価格競争に陥りやすくなります。
差別化は「料理」だけでなく、「サービス」「雰囲気」「ストーリー」など多角的に考えることが効果的です。顧客の心に強く印象付け、「この店でなければならない理由」を創出することで、持続的な競争優位性を確立できます。
顧客データを活用する
飲食店マーケティングにおいては、顧客の来店頻度、好みのメニュー、特別な日などの情報の収集・分析も肝要です。CRM(顧客関係管理)システムを活用して、顧客データを一元管理することでマーケティングが可能になります。
また、データに基づいたアプローチにより、的確なタイミングで最適な提案ができます。「勘」や「経験」だけに頼らないアプローチであり、経営判断と顧客満足度向上の両立を可能にしましょう。
継続的な情報発信を行う
飲食店マーケティングを行うなら、定期的に店舗の情報を発信し続けることで、顧客の記憶に残り、来店のきっかけを作ることが重要です。SNS、ブログ、メルマガなどを活用して、新メニュー情報、イベント告知、日々の店舗の様子などを伝えましょう。
継続的な情報発信は、店舗のブランド形成や顧客との関係強化にも貢献します。単なる告知活動ではなく、ブランドと顧客との間の強固な関係を築くための戦略的な取り組みなのです。
品質の維持向上に努める
飲食店マーケティングの基本は、料理の味やサービスの質など、提供する価値の一貫性と向上です。どれだけ宣伝しても、実際の体験が期待に応えられなければリピートにつながりません。
「ハードワークを継続する」ことがマーケティングの第3ステップであり、日々の努力の積み重ねを求められます。「手を抜かずに誠実に仕事をし、毎日、毎月、毎年続けること」が、もっとも有効的なマーケティングになるのです。
効果測定を定期的に行う
飲食店マーケティングでは、実施した施策の効果を数値で把握し、次の戦略に活かすことサイクルも確立します。「何となく効果があった」ではなく、具体的な数字で効果を測定することで、投資対効果の高い施策を見極められます。
売上、客数、客単価、リピート率など、目的に応じた指標を設定して追跡しましょう。
- SNS投稿の反応(いいね数、シェア数、コメント数)
- クーポンの利用率や特定メニューの注文数
- 新規顧客とリピーター比率の変化
効果測定を行わないと、効果のない施策に時間とコストを費やし続けるリスクがあります。
長期的な視点で取り組む
飲食店マーケティングという取り組みは、短期的な売上アップだけでなく、持続的な成長を目指す長期的な施策です。一時的なキャンペーンやイベントだけでは、その場限りの効果に終わってしまう可能性が高いでしょう。
ブランド構築、顧客との信頼関係、地域での評判など、時間をかけて築くべき価値に投資する視点を持ってください。マーケティングは実践から効果が出るまでに時間差があるため、すぐに結果が出なくても継続することが大切です。
飲食店のマーケティングで実施できる7つの手法
飲食店のマーケティングでは、さまざまな手法を組み合わせて行うことが効果的です。ここでは、効果が高いと言われる7つの手法を紹介します。
SNSでの情報発信
Instagram、X(エックス)、Facebook、TikTokなどのSNSは低コストで高い効果が期待できる手法です。視覚的に料理や店舗の雰囲気を伝えられるため、飲食店との相性が良いと言えます。
また、SNSごとに主要ユーザー層や特性が異なるため、ターゲットに合わせた使い分けが効果的です。魅力の発信と口コミの拡散を通じて、認知拡大と来店動機の創出を実現できます。
ホームページの作成
ホームページは店舗の基本情報やメニュー、こだわりなどを詳しく伝えられる自社メディアです。SNSと異なり、情報の網羅性や信頼性が高く、予約フォームなどの機能も実装可能です。
SEO対策を施すことで、検索エンジンからの集客も期待できます。ホームページは一度作って終わりではなく、定期的な更新や情報の鮮度維持が必要です。
MEO対策
MEO(Map Engine Optimization)は、Google Mapsなどの地図検索で上位表示を目指す施策です。「〇〇駅 ランチ」「近くの居酒屋」など、位置情報を含む検索で店舗が見つかりやすくなります。
スマホの普及により、外出先で地図アプリから飲食店を探す消費者が増加している現状に対応する施策です。MEO対策は比較的コストがかからず、地域密着型の飲食店にとっても即実践したいマーケティング手法です。
グルメサイトへの掲載
食べログ、ぐるなび、ホットペッパーグルメなどのグルメサイトへの掲載は、即効性の高い集客手段です。飲食店を探している顧客が多く利用するプラットフォームであり、新規顧客の獲得に有効です。
場合によっては、有料プランを契約することで、検索上位表示や特集掲載などの優遇措置を受けられます。グルメサイトは月額費用や送客手数料などのコストがかかるため、費用対効果を定期的に検証することが大切です。
オンライン予約システムの導入
オンライン予約システムの導入であれば、顧客の利便性向上と業務効率化を同時に実現できます。24時間いつでも予約可能となり、電話予約が億劫な顧客層の取り込みにも良いでしょう。
運用により、予約データを蓄積・分析することで、顧客管理やマーケティング施策の最適化にも活用できます。オンライン予約に対応していない場合、機会損失につながる可能性があるため、現代の飲食店には必須の機能となりつつあります。
デリバリーサービスへの参画
Uber Eats、出前館などのデリバリーサービスへの参画は、店舗の物理的制約を超えた売上拡大の手段です。コロナ禍を経て定着したデリバリー需要を取り込み、新たな顧客層の開拓が可能になります。
昨今では、実店舗とは別に、デリバリー専門のメニュー開発やバーチャルレストランの展開も選択肢になってきました。デリバリーサービスは手数料が高い場合もあるため、原価や利益率を考慮したメニュー設計をすることが大切です。
地域イベントへの参加
地域のお祭りやイベントへの出店・協賛は、地域住民との接点を作る手段です。地域コミュニティとの関係構築や店舗の認知度向上に貢献し、地域に根ざした店舗イメージを形成します。
普段店舗に来ない層にも料理を試してもらえる機会となり、新規顧客の開拓にもつながります。地域イベントへの参加は短期的な売上よりも、長期的な関係構築、ひいては認知度向上を目的とした投資と考えるべきでしょう。
飲食店のマーケティングでは香り印刷がおすすめ

飲食店のマーケティングでは、視覚や聴覚だけでなく、嗅覚にも訴えかける手法が有効です。プルーストのような香り印刷を活用することで、他店との差別化を図り、より記憶に残るマーケティングを実現できます。
チラシの配布で新規顧客に印象を強く残せる
チラシ配布は、地域住民に直接アプローチできる飲食店のマーケティングで取り入れやすい手法です。ポスティング、新聞折込、店頭配布など、目的に応じた配布方法を選択できます。
通常のチラシに香りを付けることで、視覚だけでなく嗅覚にも訴えかけ、強い印象を残すことができます。「擦って、香ってみてください」というインパクトで、通常のチラシよりも高い訴求力を発揮するでしょう。
【関連記事】販促に効果的なチラシ作成のポイントとおすすめのデザイン事例
ポストカードでリピーターや常連客へもアプローチできる
ポストカードでは、手書き風のメッセージや写真を添えることで、親しみや信頼感を演出できます。店頭での手渡し、郵送、提携店舗での設置など、柔軟な配布方法が可能です。
香り印刷所プルーストのハガキサイズの香りポストカードは、リピーターや常連客への感謝や再来店を促す目的に適しています。季節限定メニューの案内やイベント告知、誕生日特典などと組み合わせて反応率を高め、ファン化につなげることが可能ですので、ぜひ商品ページをご覧ください。
【関連記事】効果的なポストカード作成のコツとおすすめのデザイン例
飲食店のマーケティングを行う際の注意点
マーケティングを実践するためには、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。以下に、意識すべき4つのポイントを紹介します。
ターゲットを広げすぎない
ターゲットが曖昧になると、メニュー開発、価格設定、店舗デザイン、販促方法など、すべての施策に一貫性がなくなってしまいます。このように、だれにも強く支持されない「中途半端な店」になってしまうリスクがあります。
ターゲットを絞ることは「だれかを排除する」ことでもありますが、特定の層に強く支持される店にになる有効な手段です。「だれにでも」ではなく「だれかに確実に」価値を提供するという原則を忘れないようにしましょう。
一時的な集客だけで終わらせない
よくあるのが、「10%OFF」「ビール1杯無料」などのクーポンです。もちろん、来店のきっかけになりますが、それだけでは顧客との長期的な関係構築は難しいでしょう。
新規顧客獲得コストはリピーター維持コストの5倍とも言われており、一時的な集客だけでは費用対効果が低くなります。「集客」と「顧客維持」を別々に考えるのではなく、顧客の生涯価値を高める一連のプロセスとして捉えることが大切です。
デジタルかアナログに偏りすぎない
SNSやWeb広告だけに注力し、店頭での販促や地域とのつながりを軽視するケースがあります。逆に、チラシやDMなど従来型の手法だけに頼り、デジタルの可能性を活かせていないケースもあります。
顧客の情報収集や購買行動は多様化しており、複数のチャネルを組み合わせたアプローチが効果的です。
効果測定は手を抜かない
「なんとなく効果があった気がする」という感覚的な判断だけでは、投資対効果の低い施策に時間とコストを費やし続けるリスクがあります。
数値化できる指標を設定し、定期的に効果を検証することで、PDCAサイクルを回すことが重要です。効果測定を行わないと、「何が成功で、何が失敗だったのか」の判断ができず、改善のサイクルが回らなくなるでしょう。
よくある質問(FAQ)

最後に、飲食店のマーケティングについて、経営者の方からよく寄せられる質問にお答えします。
飲食店の三大要素は何ですか?
飲食店の三大要素は、「人・物・場」の3つです。
| 項目 | 説明 | 例 |
| 「人」 | スタッフのサービス品質やホスピタリティ、顧客との関係性を指す | 接客の質、スタッフの教育、チームワーク |
| 「物」 | 料理の味や品質、メニュー構成、食材の鮮度などの提供する商品 | 料理の味、見た目、独自性、コストパフォーマンス |
| 「場」 | 店舗の立地、内装、雰囲気、空間設計など顧客体験を形作る環境要素 | 立地条件、店内デザイン、清潔感、居心地の良さ |
どれか1つでも欠けると総合的な満足度が低下し、持続的な経営が難しくなってしまいます。
飲食店のKPIとは何ですか?
飲食店のKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)とは、マーケティングや経営の成果を測定するための数値指標のことです。売上、客数、客単価、回転率などの基本指標から、リピート率、顧客満足度などの顧客関連指標まで多岐にわたります。
KPIを設定・測定することで、目標達成度の確認や改善点の発見が可能になります。
| 項目 | 内容 |
| 売上関連 | 総売上、客単価、売上構成比 |
| 顧客関連 | 来店客数、リピート率、新規顧客数 |
| 運営関連 | 回転率、原価率、人件費率 |
| マーケティング関連 | SNSフォロワー数、予約率、クーポン利用率 |
KPIは単に数値を追うだけでなく、その背景や要因を分析し、改善策を講じることが重要です。
飲食店の売上が減少する原因は何ですか?
飲食店の売上が減少する原因は多岐にわたりますが、主な要因としては競合との差別化不足、顧客ニーズの変化への対応の遅れ、マーケティング施策の不足などが挙げられます。外部環境の変化(コロナ禍など)や消費者の行動変容(デリバリー利用増加など)にも影響を受けます。
そのほか、SNSでのネガティブな口コミや評判も、売上減少に直結する可能性があります。
- メニューのマンネリ化や品質低下
- スタッフのサービス品質の低下
- 競合店の新規出店や強化
- 情報発信の不足や顧客とのコミュニケーション不足
など、売上減少の兆候を早期に察知し、顧客満足度調査や競合分析を通じて原因を特定し、迅速に対策を講じることが重要です。
まとめ
飲食店のマーケティングは、単なる宣伝活動ではなく、お客様のニーズを理解し、それに応える価値を提供する総合的な取り組みです。競争が激化する飲食業界で生き残るためには、ターゲットを明確にし、差別化を図り、継続的な情報発信と品質向上に努めることが不可欠です。
なかでも、香り付きチラシやポストカードは、視覚だけでなく嗅覚にも訴えかけることで、強い印象を残し、他店との差別化を図ることができます。香りによって記憶と感情を呼び起こす「プルースト効果」を活用することで、お客様の心に残る飲食店になることができるでしょう。
飲食店も、香りを活用した印象的なマーケティングを始めてみませんか?香り印刷所プルーストのサンプル請求から、新しいマーケティングの可能性を体験してください。
香りの印刷所プルースト編集部
この記事は、香りの印刷所プルーストを運営している久保井インキ株式会社のプルースト編集部が企画・執筆した記事です。
香りの印刷所プルーストでは、香りの印刷をテーマにお役立ち情報の発信をしています。