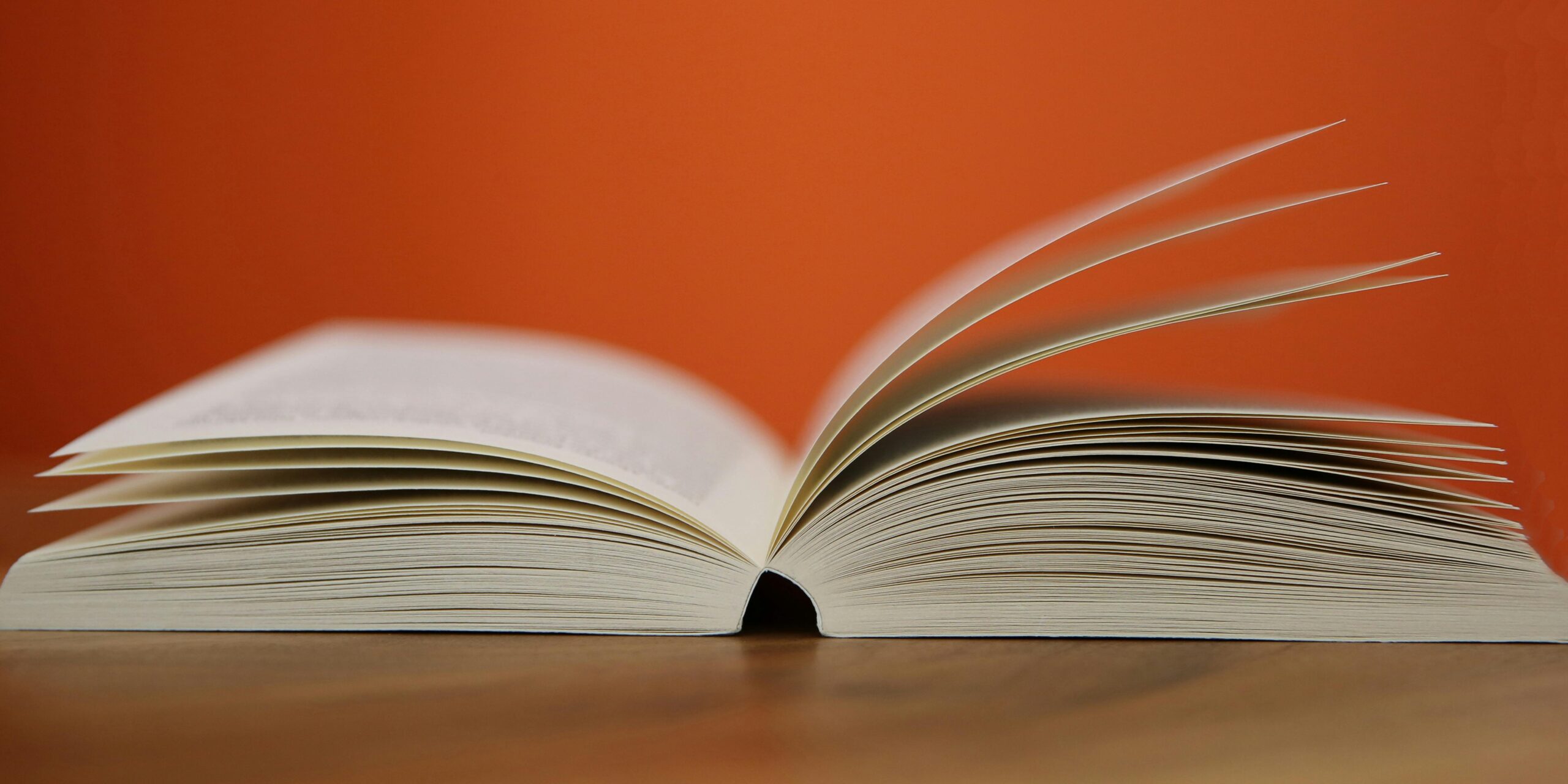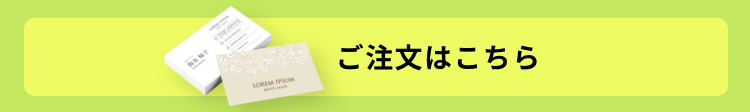コラム
マーケティングのベネフィットとは?意味や違いから見つけ方まで詳しく解説

マーケティングの現場で「ベネフィット」という言葉をよく聞きますが、その正確な意味を理解している人は意外と少ないものです。商品の機能を説明するだけでは顧客の心に響かず、売上向上につながらない理由もここにあります。
商品やサービスの特徴(メリット)を伝えるだけに限らず、それ以上に「顧客がその商品から何を得られるのか」を明確に示すベネフィットの理解が欠かせません。本記事では、マーケティングにおけるベネフィットの基本概念から実践的な活用方法までわかりやすく解説します。
Index
マーケティングにおけるベネフィットとは
ベネフィットとは「顧客が商品やサービスから得られる価値や利益」を指すマーケティング用語のことです。機能や特徴によって顧客の生活をどのように改善できるか、どのような問題を解決できるかを示すものです。
例えば、高性能カメラ付きスマホの場合、「美しい写真が撮影できる」が機能、「大切な思い出を鮮明に残せる」がベネフィットとなります。顧客はベネフィットに価値を感じて購入を決断するため、マーケティング戦略において極めて重要な概念です。
ベネフィットとエンドベネフィットの違い
ベネフィットとは、商品・サービスを使って得られる直接的・機能的な利点を指します。一方、エンドベネフィットはその先にある最終的・感情的な価値を意味します。
例えば「移動時間の短縮」がベネフィット、「家族と過ごす時間が増えて幸福感も得られる」がエンドベネフィットです。マーケティングでは、顧客により深い価値を訴求するべく、最終的に求めている価値(エンドベネフィット)まで考えてください。
ベネフィットと価値の違い
ベネフィットは、商品・サービスの利用によって得られる具体的な利得や効能です。価値は、このベネフィットを通じて得られる主観的な満足や意味合いを含む広義の概念です。
ベネフィットは価値を構成する一要素に過ぎません。価値には、顧客の価値観やライフスタイル、社会的な文脈なども含むため、ベネフィットよりも総合的な概念として理解してください。
ベネフィットとメリットの違い
ベネフィットは、顧客視点で得られる利得や恩恵を指し、感情的・未来的な側面も含みます。一方、メリットは製品やサービスの特徴に基づく利点で、客観的・機能的な側面が強いものです。
メリットは企業視点、ベネフィットは顧客視点の表現だと考えればわかりやすくなります。例えば、掃除機の「吸引力」がメリットで、「短時間で部屋がきれいになり、自由な時間が増える」がベネフィットです。
マーケティングのベネフィットの種類
ベネフィットの種類は、経営学者のデイビッド・A・アーカー氏による3つの分類が基本です。以下で、それぞれのベネフィットをわかりやすく説明します。
機能的ベネフィット
機能的ベネフィットとは、商品やサービスが持つ機能、および品質により得られる利益のことです。思いつきにくいかもしれませんが、「時間短縮」「作業効率向上」「コスト削減」などが代表例です。
顧客の日常的な問題解決に直結するため、購買決定において重要な要因の1つです。論理的な判断基準として活用でき、競合商品との比較・検討時に重視するベネフィットでもあります。マーケティングでは、具体的な数値や測定可能な効果を示して訴求力を高めるといった際に重宝します。
情緒的ベネフィット
情緒的ベネフィットとは、商品やサービスの利用を通して、消費者が特定の感情・気持ちをいだく状態を指します。よく広告等で見られるのは、「安心感」「優越感」「リラックス効果」などです。
顧客の感情に訴えかけるため、ブランディングや差別化戦略において極めて役割を果たします。機能面では同等の商品でも、情緒的ベネフィットの違いによって選びやすく、長期的に見た顧客との関係構築にも役立ちます。
自己表現ベネフィット
自己表現ベネフィットとは、商品・サービスを手に入れてはじめて実現する、自己表現・自己実現に関するベネフィットのことです。わかりにくい概念ですが、「個性の表現」「ステータスの向上」「理想の実現」などが例です。
例えば、環境に配慮した商品を選んだ結果、「環境意識の高い人」というアイデンティティを表現できる、というのが自己表現ベネフィットです。顧客の価値観やライフスタイルと密接に関連しており、高価格帯の商品やサービスのマーケティングで重視する傾向があります。
マーケティングでベネフィットが重要な6つの理由

ではなぜ、マーケティングでベネフィットを意識するべきなのでしょうか。ここでは、マーケティング戦略においてベネフィットが重要な理由を6つの観点から解説します。
顧客の購買意欲を高める
まず、ベネフィットは顧客の感情に直接訴えかけ、商品への関心と購買意欲を向上できます。機能説明だけでは、「なぜいまの自分に必要なのか」は伝わりにくいからです。
ベネフィットを示していれば顧客は具体的な価値をイメージでき、結果として検討期間の短縮と成約率の向上が期待できます。この納得感が購買行動を後押しする要因となり、「欲しい」という感情を呼び起こして自然な購入動機を生み出します。
競合他社と差別化できる
似たような機能を持つ商品が溢れる現代において、マーケティングのベネフィットは差別化の手段ともなります。同じ機能でも、顧客に提供する価値の表現方法によって印象は変わるためです。
独自のベネフィットを明確に示せば価格競争に巻き込まれず、付加価値での勝負が可能です。低価格を求める顧客層とは別の層へアプローチできれば、「唯一無二の選択肢」としての認識も獲得できます。結果、競合商品との比較・検討時に優位に立てるポジショニングを目指せるのです。
【関連記事】差別化戦略の成功例10選!具体的な事例から学ぶ競争優位の作り方と香りの活用法を解説
価格以上の価値を伝えられる
マーケティングでベネフィットが明確に伝わると、顧客は価格以上の価値を感じます。機能だけの説明では価格の妥当性を示すのが困難ですが、利益を示せば高価格でも『納得』して購入に至れるからです。
こういった手法を、よくプレミアム戦略と呼びます。平たくいえば「高いから駄目」ではなく、「高いから品質が良い」というイメージを持ってもらいます。価格に敏感でない層、富裕層、ステータス志向層を狙えるほか、価値に見合った価格設定が可能になり、マーケティングROI(投資収益率)の向上にもつながる手法です。
顧客の満足度を高められる
ベネフィットを正しく伝えれば、顧客の期待値と、実際の体験におけるギャップの最小化も狙えます。購入前に得られる価値を具体的に理解していれば商品使用時の満足度は高くなりますし、その逆であれば反感を買います。
期待通りの価値を得られた顧客であれば、その体験に対して高い価値(お金)を払うのに抵抗はなくなり、リピート購入や口コミによる推奨行動を取りやすくなります(※)。この長期的な顧客関係の構築につながる要因は、マーケティングにおけるLTV(顧客生涯価値)の向上にも役立つのです。
参照:Customer experience is everything: PwC
マーケティング効率を最適化できる
マーケティングでベネフィットを明確に定義すれば、ターゲット顧客の特定とメッセージング戦略の構築も可能です。どの顧客層がどのベネフィットを重視するかを理解し、無駄な広告費を削減できればROIも向上できるためです。
通常、マーケティング予算は湯水の如く使えるリソースではありません。限られているからこそ、どこまで効果を高め、効率も同時に実現できるかが焦点です。うまく最適化できればセグメント別にアプローチできますし、パーソナライズしたマーケティング施策の実行にもつながります。
ブランド価値を向上できる
最後に、一貫したベネフィットの訴求は、ブランドの価値観やポジショニングを明確にし、ブランド力の向上に役立ちます。顧客がそのブランドから得られる価値を理解すれば、ブランドへの信頼感と愛着が深まるからです。
確かに、「AならB社だ」、「CならD社だ」というブランドの第一想起へ至るには、相応の費用と時間を要します。しかし、ブランドロイヤルティの向上と、長期的な競争優位性の確立を実現できれば、自社が保有する持続的な成長の基盤となるのです。
マーケティングのベネフィットを特定する方法
ここまで良い話をお伝えしてきましたが、実際にマーケティング戦略を構築するためには、顧客が真に求めているベネフィットを正確に特定しなければなりません。ここでは、実施を検討できるベネフィットを特定する方法を5つ紹介します。
顧客インタビュー
第一に、実際の顧客や見込み顧客に対して直接インタビューを行い、商品に対する本音や期待を聞き出す方法です。「なぜその商品を選んだのか」「使用後にどのような変化があったか」などを質問します。そこから、顧客が真に価値を感じているポイントを発見するわけです。
定性的な情報が得られるため、数値では見えない深層心理を理解できます。感情的なニーズや潜在的な課題も同時に把握でき、より刺さるベネフィット設計を目指す方にも最適です。
アンケート調査
第二に、大規模な顧客層に対してアンケートを実施し、定量的なデータを集める方法です。「もっとも重視する要素・要因」「満足度の評価」などを数値化し、顧客全体の傾向を把握できます。
調査項目によりますが、統計的な分析により優先すべきベネフィットの順位付けや、セグメント別の特徴把握が可能です。同時に客観的な判断材料として活用でき、マーケティング戦略の根拠となるデータとしても有効です。
競合分析
第三に、競合他社のマーケティングメッセージや顧客レビューを分析し、市場で訴求しているベネフィットを調査する方法です。成功している競合のアプローチから学び、自社独自のベネフィットを発見するヒントを得られます。
また、競合が見落としているベネフィットを特定できれば、差別化の機会を見つけられます。SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威の分析)などであれば、マーケティングにおける市場ポジショニングの策定にも役立ちます。
ペルソナ分析
第四に、詳細な顧客ペルソナ(理想的な顧客像)を作成し、その人物の日常生活や課題、願望を深く分析する方法です。「この人がもっとも困っているのは何か」「どのような理想の状態を望んでいるか」などにより、刺さるベネフィットを特定できます。
ペルソナを作り込む際には、よく年齢、職業、ライフスタイル、価値観まで詳細に設定するよう見聞きするはずです。ただ、理想を追いすぎると「存在し得ない人物像になる」ため、データ等から割り出して精度の高い対象を導き出してください。
商品体験のモニタリング
最後に、顧客が実際に商品を使用している場面を観察し、その行動や反応からベネフィットを発見する方法です。エスノグラフィー調査や、ユーザビリティテストなどの手法を活用します。
主に、顧客が言葉で表現できない潜在的な価値や、想定外の使用方法から新たなベネフィットを見つけられます。実際に体験してもらう方法であれば真のニーズを明らかにしやすくなりますし、マーケティング戦略に新たな視点を取り入れるきっかけにもなります。
マーケティングのベネフィットの活用シーン

ここからは、マーケティングのベネフィットの活用シーンと、例としてその使い方を解説します。これから役立てたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
営業活動
営業プレゼンテーションにおいて、商品の機能説明よりもベネフィットを中心とした提案を行えば成約率の向上を狙えます。顧客の課題や目標を事前にヒアリングし、対応するベネフィットを明確に示してください。
「この商品によって会社はこんな風に改善できます」という具体的な価値提案が顧客の心を動かすきっかけになります。説得力の向上には、数値で表現できる効果(コスト削減額、時間短縮効果など)と感情的な価値(安心感、信頼感など)を組み合わせるのも有効です。
広告・宣伝
広告のキャッチコピーやビジュアルにベネフィットを取り入れ、顧客の関心を引きつけられれば、具体的なアクションにつなげられます。商品の特徴を羅列するのではなく、「生活がこう変わります」というメッセージで訴求するのが基本です。
SNS広告やランディングページでも、ベネフィットを前面に出した構成はよく取り入れられます。マーケティングキャンペーンでは、機能的・情緒的・自己表現ベネフィットをバランスよく組み合わせて、幅広いターゲット層に訴求してください。
コンテンツ制作
ブログ記事、動画、パンフレットなどのコンテンツ制作においてベネフィットを軸とした構成にすると、読者の興味を維持できます。内容にもよりますが、「使い方」よりも「使った結果どうなるか」に焦点を当てた内容にするといった具合です。
顧客の成功事例やビフォーアフターを示し、ベネフィットを具体的にイメージしてもらうのもよくある手法です。マーケティングのコンテンツ制作では、読者の立場に立った情報提供を心がけ、自分事として捉えてもらえるような構成でベネフィットを伝えてください。
商品開発
新商品の企画段階から、どのようなベネフィットを提供するかを明確に定義できれば、市場ニーズに合致した商品開発も狙えます。機能ありきではなく、顧客価値ありきで商品を設計するためにベネフィットが役立ちます。
また、開発チーム全体でベネフィットを共有し、一貫性のある商品コンセプトを確立する指針に使えるのも利点です。顧客視点での価値創造の実現は、マーケティング部門と開発部門などの連携だからこそ生まれます。
【関連記事】マーケティングの手法は何がある?決め方と新たなトレンドの「香り」を解説
マーケティングのベネフィット設計を成功させるためのポイント
ここからは、マーケティングのベネフィット設計を成功させるポイントを解説します。よくある失敗を減らすためにも、ぜひ確認してから取り組んでください。
企業視点での価値を押し付けない
マーケティングのベネフィット設計でよく陥るのが、企業が考える価値と、顧客が実際に求める価値におけるギャップです。技術者や開発者の視点で「すごい機能」だと思っても、顧客にとっては不要だったというケースはよくあります。
成功するベネフィットとは、顧客の立場に立って本当に必要な価値を見極めた言葉です。定期的な顧客調査により社内の思い込みを排除し、企業視点の偏りを修正しつつ顧客中心に調整してください。
曖昧で具体性に欠ける表現は使わない
「快適さ」「便利さ」 「満足感」といった抽象的な表現では、顧客に具体的な価値が伝わりにくくなります。顧客が実際に体験できる変化や結果を、数値や事例を用いて具体的に示してください。
具体的には、「30分の時短」「年間10万円の節約」のように、測定可能で実感できるベネフィットの表現を心がけます。マーケティングメッセージでは、顧客が自らの状況に置き換えて想像できる具体性が有効です。
ターゲット設定を見誤らない
非常に残念ながら、すべての顧客に同じベネフィットが刺さるわけではありません。年齢、職業、ライフスタイルによって重視する価値は異なります。このタイミングでターゲットを明確に定義せずにベネフィットを設計すると、だれにも響かないメッセージになってしまいます。
セグメント別に最適化したベネフィットの訴求は、常に意識してブラッシュアップしてください。ペルソナ設定とベネフィット設計を連動できれば、効果の高いアプローチが可能になります。
香り印刷を活用したマーケティングのベネフィットの事例

弊社プルーストでは、香り印刷という技術を用いたマーケティング手法をご提案しております。実際に、どのようなベネフィットが創出できているかの具体的な事例をご紹介いたします。
エレメンツ社労士事務所
まず、士業の中でもとくに堅い印象を持たれやすい社会保険労務士という職種において、香り付き名刺を活用した事例です。フローラル系の香りを名刺に施し、「この名刺、いい香りがしますね」といった自然な会話のきっかけを生み出しました。
単なる名刺交換の場を感情的なつながりを感じてもらえる『特別な体験』へ昇華させ、初対面時の心理的なハードルを下げる工夫に一役買っています。この取り組みは、機能的(記憶に残る)、情緒的(親しみやすさ)、自己表現ベネフィット(顧客思いの専門家としてのアピール)という3つのベネフィットを同時に実現した好例です。
【事例】香りの印刷所 プルーストの事例:エレメンツ社労士事務所様
大阪産業創造館
次に、展示会への来場促進を目的としたDM施策の一環として、香り付きハガキを使用した事例です。通常のハガキでは埋もれがちな案内状に香りという感覚的な仕掛けを加え、「面白い」「気になる」という反応を引き出しました。
特にイベントや販促において、視覚情報に加えて嗅覚を使った訴求は認知・記憶への定着率を高めるベネフィットとなります。女性来場者の比率増加という具体的成果にもつながり、従来のDMでは実現困難な強い印象づけに成功した好例です。
まとめ
ベネフィットとは「顧客が商品・サービスから得られる価値(利益・恩恵)」のことで、単なる機能説明(メリット)ではなく「顧客の問題解決や願望実現にどう貢献するか」を示すものです。とはいえ、現代のマーケティングにおいて、商品の特徴だけを伝えても顧客の心は動きません。
顧客が真に求めているのは、自らが得られる具体的な価値や理想の未来です。香り印刷では、見た目のインパクトに加えて嗅覚へ訴えて記憶に残る体験を創出できます。商品やサービスに新たな価値を付加し、競合との明確な差別化を実現したい方はぜひ以下からプルーストをご覧ください。
香りの印刷所プルースト編集部
この記事は、香りの印刷所プルーストを運営している久保井インキ株式会社のプルースト編集部が企画・執筆した記事です。
香りの印刷所プルーストでは、香りの印刷をテーマにお役立ち情報の発信をしています。